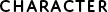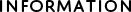Special
プロローグストーリー・Side 窪田 縁
「演奏お疲れさん」
「ども〜」
「今日はヘルプか?」
「そんなとこ」
馴染みのライブハウスのバーカウンターで、見知ったスタッフに挨拶をしながら注文したドリンクが出てくるのを待つ。ライブの後には度数の高めのものを飲むのがいつものオレのスタイルだ。
「なあ、こっちに戻ってくる気はないんだよな? 良い腕してるのにもったいない」
「まあな……今は絵の方が忙しいし」
「そうか。こっちに戻りたくなったらいつでも声かけろよな」
「ああ。その時はよろしく」
スタッフからグラスを受け取ったオレは、ライブハウスの中を見回す。暗いホールの中で目当ての人物が見つかるかと心配になったが、案外すぐに見つかった。ステージがよく見える後方の壁際に場所を確保していたらしい。
(確かにここならよく見えるな)
じっとステージを見つめていたが、隣に立つとオレに気づいたようで赤みがかった瞳と視線がぶつかった。
「よ、絃静。ここにいたんだな」
そう声をかけてみたものの、おそらくこの爆音が響く中では何も聞き取れないだろう。絃静が手にしていたグラスを持ち上げたのを見て、オレも同じようにグラスを持ち上げてフチを重ねる。グラスとグラスが触れる音の代わりに、ドラムの音がホールの中に響いた。
ふとステージに視線を移せば、カラフルなライトが演者を彩っているのが飛び込んできた。
(さっきまであそこにいたんだよな)
楽しそうに演奏している奴を見ていると、オレもこんな風に見えていたのかなんて思う。オレがベースを片手にステージに立っていたのは、昔のバンド仲間から頼まれたからだった。
昔は本気でバンドをしていたときもあったけれど、今はただの気分転換でしかない。絵を描くためのインスピレーションをもらうため、といえばそれっぽいだろうか。
ここは、音楽やバンドが好きで、音楽を聴いたり楽器を弾きたい奴らが集まる場所なのに、中には違う理由でこういうところに来る奴もいる。
(例えばこいつ)
ふと絃静を見ると、絃静は少し表情を和らげながらステージを見つめていた。それはまるで美術館で気に入った絵を見つけた時のような……そんな表情をしているようにも見える。
絃静がライブハウスに来るのは、絵を描くインスピレーションをもらうためではない。いつだったか絃静の口から聞いた理由。それは「音が絵に見える」だった。
そう、絃静は音楽を聞きに来たわけでもインスピレーションをもらうためでもなく、絵を見にここにいるのだった。
(オレには音は見えないし、音は音でしかないけど)
絵は絵だし、音は音だ。そもそも視覚と聴覚で使っている部分も違うのだから、同じわけがないのに。
それでもホールの中に響く爆音が響いている今も、こいつの目には何かしらの絵に見えているのだろう。
(今でも信じられないけどな)
正気を疑うような発言でも、絃静なら不思議と納得させられてしまう。絃静の持つ雰囲気がそうさせているのかもしれない。
グラスを片手にしばらく曲を楽しんでいると、ちょうど出演しているバンドが演奏を終えて楽屋へと引っ込んでいった。入れ替わるようにして別のバンドが準備を始め、それに合わせてホールが明るくなる。準備が終わるまでの小休憩だ。
スタッフの顔ぶれをぼんやりと眺めながら待っていると絃静が口を開いた。
「……そういえばさ」
「ん?」
絃静が何気なく話し始めたのは、冗談のような話だった。
「新しい家族ができるみたいなんだよ」
「……は?」
「母親と妹ができるらしい」
「らしいって」
絃静の言葉は妙に他人事で現実味がなく、むしろここまでくると絃静なりの冗談じゃないかと思えてくる。それこそ、音が絵に見えると言ったときと同じように。
「で、どこで誘拐してくる予定なんだ?」
「……」
軽口を叩くと、絃静はふいっと顔をそらした。拗ねているところを見ると、本気で言っていたらしい。
つまり、父親の再婚で母親と妹ができるのは事実だということだ。
(冗談じゃないってことか)
じっと観察してみれば、絃静の瞳の中には不安と期待が入り混じっているのが分かった。自分をとりまく環境が否応なしに変わるのだから、当然の反応かもしれない。
思えば、絃静は才能には恵まれていても、家族には恵まれていなかった。
(まあ、その方が不公平感がなくていいからオレは好きだ)
黒住絃静という男は、見た目もよくて、絵の才能もあって、人を惹きつける力もある。
だから一見、多くの人が欲しくても手に入れられないものを最初から持っている奴だ、なんて思われていることも知っている。どこかにマイナスがあったっていいのに、なんてやっかみじみた複雑な視線を向けられていることもある。
確かにそう思いたくなるのも分からなくはない。絃静はなんでも『持ってる』側の奴だと思えてしまうから。
だがそんな視線を向けられた絃静本人は、心のどこかでマイナスになるものを望んでいるように思うこともある。絃静の中にある少し不安定で仄暗いものを望む欲求が、瞳の奥底に見える瞬間がある。……ような気がする。
(肝心な事は何も話さないから、本当のところはどうかわからないけどな)
「新しく家族ができることに関してはどう思ってんだ? 嬉しかったりすんの?」
その問いかけに絃静は少し悩んでから、曖昧な返事を寄越した。
「……どうなんだろう」
「ふ〜ん。じゃあ、新しい家族ちゃん可愛い?」
言葉の代わりに、怪訝そうな表情が返ってくる。その後にボソリと「同じ大学。縁も見たことあるかもな」と口にした。
絃静に新しく家族ができるだけでも驚きだというのに、ましてや同じ大学だなんて、厄介な事になったな。
(見たことあるって言われても、オンナはいろいろいるしな……)
頭の中で今まで会ったオンナのことを思い出そうとするけれど……当然、誰だか分かるはずもない。絃静の妹になったのだからそのうち会う機会もあるだろうし、なんなら理由を付けて会いにいこうと心に決めて、口を開く。
「じゃあ、新しい家族ちゃんもらっちゃおう」
「……」
再び冗談を口にすれば、無言のまま今度ははっきりと睨まれた。それは本意ではないということで……視線の強さだけで、絃静の本音が垣間見えた。
絃静にその視線を向けられるのことを面白いと思う一方で、どこか冷めた気持ちにもなる。
(はいはい、そういうことはするなってことな。冗談だっての)
絃静の反応にどこか白けた気持ちになりかけたときに、知った声が聞こえた。
「お、こんなとこにいたんだな〜」
「よお、久しぶりだな」
声をかけてきたのは、ここのライブハウスで働く友人だった。そいつはドラムをやっているが、今日はスタッフとしてではなくバンドマンとして純粋に遊びに来たらしい。
絃静から少し離れて、軽くグラスを合わせて乾杯する。
「最近どうなんだ〜?」
「それなりだな。そっちも大変なんだっけ?」
「まあな。でも、それも込みで楽しませてもらってるよ。うちのヴォーカル、実力はあるのに気分屋でな〜」
「ああ、前にそんなこと言ってたな」
そいつと近況を話しながら横目で絃静を見ると、困っているようなにやけているような……なんとも複雑そうな表情をしている。
どんなに欲しいと望んで手を伸ばし、それを手に入れるために努力をしたとしても、手に入らないものはある。生まれた時に、神様がそうジャッジして振り分けた。
特にオレと絃静はそれが顕著なように思えた。
オレの望みが叶わないように、絃静の望みも叶わない。だからこそ、オレたちは不必要なものだけは人よりも恵まれているのだ。
そう思うことにして、納得させてきたけれど……胸によぎるのは一抹の不安にも似た胸糞悪い感情。
「新しい家族ちゃん……」
無意識に呟いたことでドラマーの友人が怪訝な表情を浮かべていたが、話を続ければ流してくれたようだった。
その後もしばらく話をしていたが、適当なところで会話を切り上げて絃静の元に戻る。
そのタイミングで、ホールの明かりが落ちた。次のバンドの準備が終わったようで、間も無く演奏が始まるだろう。
演奏の調節のために鳴らしていた音も、それから演奏を待つ観客の声も消える。ほんの一瞬、ホールからすべての音が消える。
何かが起きる前は、静かだという。まるで今がその時だと言わんばかりに、オレの耳からは音が消えた。