coward
「じゃ、じゃあ」
「ああ。気をつけて帰って」
いつも通りの道。
いつも通りの体二つ分の距離。
こいつの、彼女の家の前の十字路で、いつも通り立ち止まって、いつも通り解散しようとしていた。
でも『いつも通り』と違うのは、俺たちの制服の胸には花のコサージュが飾られていて、通学カバンには卒業証書の筒が入っていること。
明日からの約束が何一つとしてないこと。
彼氏・彼女となって何ヶ月。今日という日まで、手を繋ぐことはなかったし、キスの一つもなかった。……なんてことを、今更になって思う。
けれど、こいつは他の奴らに見せている数倍はツンツンしていて、俺は俺で他の人たちに見せているよりも数倍ラフな顔を見せていた気がする。
友達を見ている限り、彼氏・彼女というのは、もっと甘酸っぱい何かがあると思っていたのだけれども、こいつとの間には特にそんな雰囲気が生まれることはなかった。『男避け』という口実で付き合い始めたせいで、距離の詰め方が分からなかったのもある。人の色恋沙汰に興味津々な年頃だから、結局周りからからかわれる回数が増えた、という結果で、もしかしたらこいつにとっては不本意な関係だったかもしれない。何も言わなかったから、知るよしもないけれど。
だけど、最初から関係を変えられなかったのは、いつも通りのやり方で付き合っても、きっとこいつは俺に心を開くことはないし、むしろ嫌われてしまうのではないか、という懸念がずっとあったせいだ。
どんな風に気持ちを伝えたらいいかを考えていたら、今日という日まで来てしまった。
「……気をつけてって、家、目の前なんだけど」
いつもならさっさと家に入っていってしまうのに、こいつは何故か今日は足を止めて、俺に向き合った。
卒業という区切りは、……高校進学と共に通う学校が別れてしまうのを、こいつなりに何か思っていてくれるのだろうか。なんて、都合のいいことを思う。
「そうだけどさ。家の目の前で〜、とかよくニュースで聞くだろ?」
「縁起でもないこと言わないで」
「ごめん、ごめん。そうでなくてもさ、お前の家、遅くまで親いないだろ? 泥棒とか気をつけて、ってこと」
「……別に、一人とか慣れてるし」
「慣れるもんじゃないだろ。一人は寂しくない?」
「一人が気楽な人もいると思う」
「お前はそのタイプ?」
「大勢が得意なタイプだと思った?」
「全然」
「……笑いながら言うこと? さっきと言ってること違うし」
「あはは、俺の願望もあるかも」
「……なにそれ」
目の前の彼女は、苦虫を潰したような、怒りだしそうな、……けれど何か物言いたげな顔をした。付き合っている時に何度か見た顔でもある。
じっとその顔を見てみるけれど、そこには何の答えものっていなくて、俺には答えが分からなかった。
「……帰る」
「うん」
「帰るから」
「分かってるよ」
いつもは聞こえる小さな「また明日」の声は、聞こえなかった。
最後にちらりと見えた顔は、なんだか泣き出しそうに見えて、俺の願望もここまで極まったか、と思った。
ぱたん、と閉められたドアを見送って、息を吐いた。
「……卒業、しちゃったなあ」
卒業のこの日まで、素直に「好き」も言えず、建前ばかりを口にした毎日だった。
言おう言おうと思った言葉は一つも喉から出ず、先延ばしにした結果がこれだ。
「……言おうと思ってたんだけどな」
卒業した俺たちは、進学先も違う俺たちは、春休みの予定の一つもなくて、進学したらどう会うのか、という話もできなかった。
けれど、連絡手段がないわけじゃない。
きっと、これが最後じゃない。
そう言い聞かせて、俺は彼女の家の前を後にした。
高校に入って二ヶ月が経った。
中学の頃より難しくなった勉強に、部活に、少し前に始めたバイト。
受験と共にリセットされた人間関係は、俺の仮面とも言える社交性を分厚くさせる一つの要因にもなっていた。
とは言え、相変わらず多方面に喧嘩を売るスタイルの幼馴染の清澄は、高校もまた同じところに通っていて、中学と変わらずつるんでいたから、息苦しさは特になかった。
忙しかった。
慣れるのに時間がかかった。
毎日が目まぐるしくて、毎日を追いかけるのに精一杯だった。
——だけどそれが言い訳であることもまた、俺はよく分かっていた。
「穂高、顔死んでる」
スマホを見ていた俺に、清澄が今日もまたストレートに指摘してきた。
「分かってても言うなって。清澄こそ、隈あるけど、どうしたー?」
「いつもの。兄弟喧嘩勃発」
「はは、流石に5人も兄弟いるとなあ。清澄は何に怒ってたの?」
「夕飯に対する態度にキレた」
「というと?」
「ビーフストロガノフが食べたいって言ったから作ったのに、ハヤシライスと変わらないとか言われた。……せっかく調べたのに」
「ロシアの料理だっけ? 作ったんだ、さっすがだな。他のお兄さんたちも?」
「全員キレてた。……ちなみに」
「ん? ちなみに?」
「全員分合わせると長編三時間。聞くなら、だけど」
「おすすめ?」
「まったく」
「じゃあやめとこうかな。でも清澄が話したくなったら言って」
「おすすめじゃないのに?」
「親友のことだろ。聞くよ」
「うわー」
「なんだよその反応」
「だから疲れるんだよ」
「疲れてないよ。普通」
「ふーん。まあ、倒れる前に言って」
「……ん、ありがと」
清澄はそれだけで済ませて、机に突っ伏した。どうやら本当に疲れているらしい。
家だったらブランケットがあるからかけてやるのだけれども、ここは学校でそういうものはないから、一言「おやすみ」とだけ言って、自分の席に戻った。
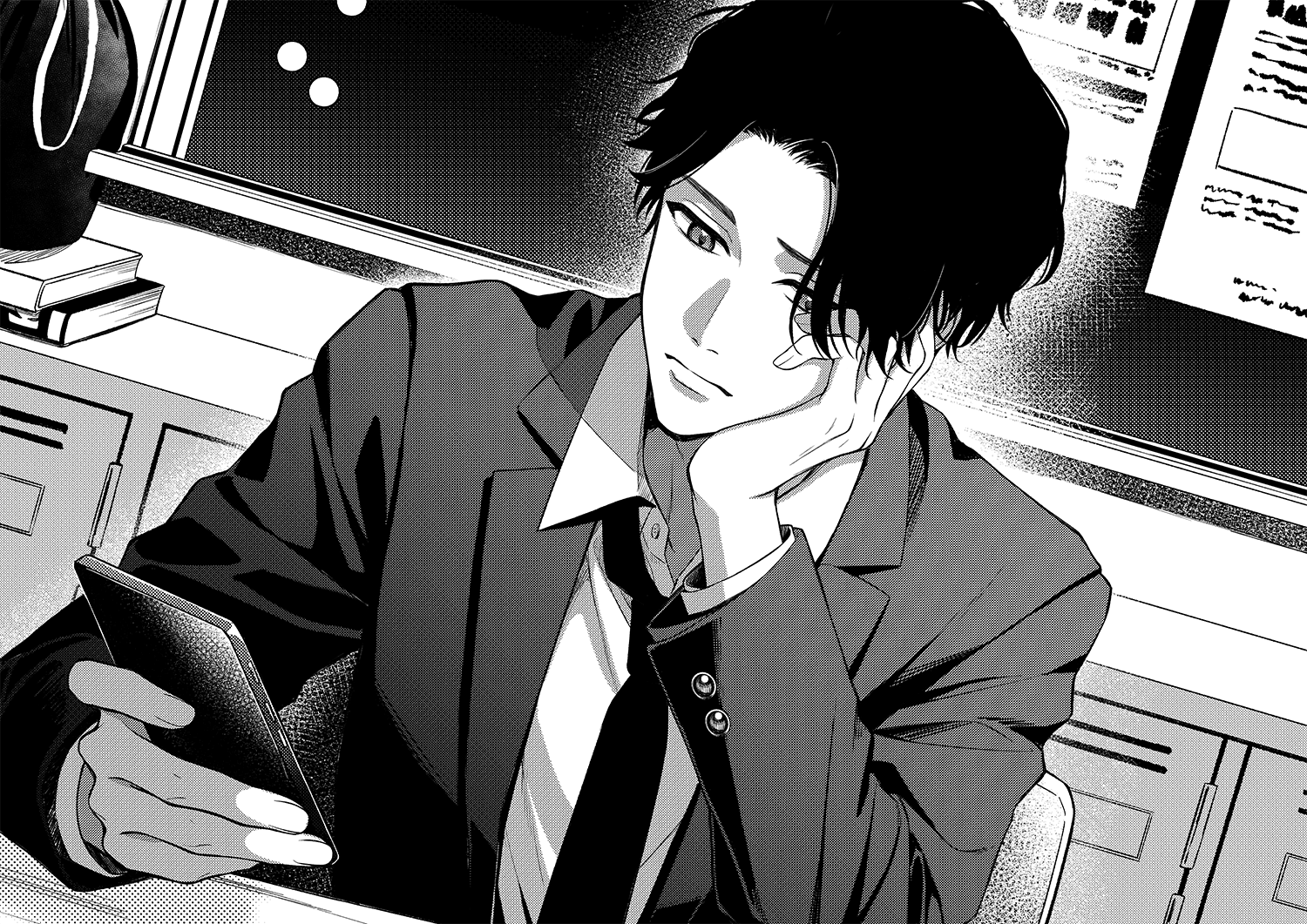
スマホをもう一度見る。通知はない。
メッセージアプリを開いて、トークルームを無意識に開く。
「……来てないよなあ」
決して筆マメな人ではなかった。話すのも得意な方ではなかった。
でも周りに迎合しないその姿が、ひどく俺にはカッコよく見えた。周りの顔色を見て、空気を読んで、円滑に回すことを優先してしまう俺には真似出来ないことだから。
彼女がどう思っていたのかは、ついぞ分からなかった。でも、お互いに流れる空気は、俺はとても好きだった。
タップした先に続く、短文のやりとり。
それが途切れたのが二ヶ月前。卒業してから、俺は、俺たちは連絡を取れないままでいる。
忙しかった。——それは本当。
慣れるのに時間がかかった。——それも本当。
でも、全部全部言い訳だった。タップすれば連絡を取れるのに、それが俺には出来なかった。
迷惑じゃないか、疲れているんじゃないか、嫌がられるんじゃないか。
中学の時は毎日のように顔を合わせていたから、簡単に言えた言葉が、言えなかった。
……きっと、いつか、……あいつが俺のことを好きでいてくれるなら、あいつから連絡してくれるだろう。
そんな淡い期待と希望が日に日にすり減って消えていく。
「あ、紫藤くん〜。この前は委員会手伝ってくれてありがと〜」
「ああ、お安い御用だって。大したことしてたわけじゃないし」
「いやほんと助かったんだって。……あ、誰かと連絡してた? も、もしかして彼女?」
「……、……いや、連絡はとってないよ」
俺は、彼女にとってなんだったんだろう?
トークルームに残る、「元気?」はずっと送れないまま。
会いたい。その気持ちはずっとあるのに。
怖くて、「会いたい」の一言が言えなかったのだ。
