encounter
進級。新しい担任に、クラス替え。
前の学年の時からのクラスメイトや、部活が同じだった人とはいい感じに過ごし、新たに関わるようになった人とは、様子見をしながら探り探り関わり合う。四月とはそういう時期だった。
そして、みんなが新しい環境に慣れようとしている時に行われるのが、『厄介ごと』——つまり、委員決めというものだ。
「じゃあ、体育委員は決まったから……、あとは図書委員だな。誰かやりたい奴はいるかー?」
先生の明るい声と相反するように、しーんと静まり返った教室。
学級委員みたいに目立つことはなく、むしろ地味な立場。お調子者は絶対選ばないだろうな、という役だ。しかも図書委員は委員会以外に、放課後に貸し出し当番があるから、余計誰も手を挙げないだろうなあ、と思っていたら案の定だった。
お前やれよ、お前こそ、というひそひそ声が聞こえるのは、三年間で見慣れた光景と言ってもよかった。
「……やります」
小さなざわめきの中、酷く冷めた声がこの「無駄な時間」を一時停止させた。
二つ前の席の女子が、まっすぐ手を挙げていた。
すっ、と伸びた背筋が印象的だった。後ろ姿しか見えないから、どんな表情をしているかは分からない。
どんな子だっけ? と思い返す。
ああ、そうだ。三年になって初めてクラスが一緒になった子だ。友達とわいわいしているタイプではなく、一人で静かに本を読んでいる印象がある。なるほど、本好きなら図書委員は苦にならないのかもしれない。委員を進んでやるタイプには思わなかったけれど。
先生はあからさまにほっとした顔をしていた。生徒側も嫌な時間だけど、先生だってやきもきする時間でもあるのは当然のことだと思った。
「お、本当か? じゃあ、一人決まりだな〜。じゃあ、もう一人、誰かいないか?」
「別に、一人でもいいんですけど」
さっき手を挙げた子が静かに言った。
周りの子も同調するように「本人が言ってるんだからいいんじゃないんですかー」なんて言うけど、先生は「二人制だからだめだ」ときっぱりと言い切っていた。それはそうだ。
また小さなざわめきが始まる。図書委員さえ決まれば終わりだから、みんな誰かにやって欲しそうで、でも誰もやりそうにない。こういう場合、友達が仕方がないなあ、という顔で便乗することもあったが、その気配は全くなかった。
さて、どうしようかな、と少し俺が考え始めた時だった。
「じゃあ、穂高がいいと思いまーす!」
友達の一人が勢いよく手を挙げて言った。
「おーい、元気よく手挙げて、他薦ってかっこ悪くないかー?」
「うるせーって。さっき学級委員は柄じゃない、とか言ってたじゃん。生徒会も同じこと言って断ってたし」
「そうだそうだ! 今までぜーんぶ回避してたんだから、そろそろやれよー」
「うわっ、否定しづらいこと言い出したー」
「紫藤くん、委員長とか出来そうだよね」
「確かにー。あんまり本読んでるイメージないけどね」
「それはそうかも」
「うっし、じゃあ、穂高が図書委員できるって思うやつー!」
ムードメーカーのクラスメイトがそう言って煽れば、そりゃあこんな雰囲気だ、みんな手を挙げるに決まっている。先生は苦笑いだ。
「こらー、お前らー、本人が手挙げてないのに勝手に決めるなー」
「先生、いいですよ別に。いつまで経っても決まらないと思いますし」
「いいのか?」
「もちろん。熱烈な推薦受けちゃいましたし、喜んで。お前ら俺のこと大好きね?」
冗談めかして周りに言えば、ブーイングと笑い声が教室を満たした。
先生が黒板に俺の名前を書く。これで委員は全て決まったわけだ。
ある意味生贄のように差し出されたわけだが、教室内の雰囲気が最悪になるよりはマシだろう。それに友達が言っていた通り、二年間委員会を回避してきたのだから、観念すべきことだとも思った。まあ、似合わないとは思うけど。
と、そこでふと思い出す。
そういえば、先に図書委員に立候補していた子は、一人だけ「穂高がいいと思うやつー!」という声に手を挙げていなかったな、と。
図書委員の仕事はその一週間後に回ってきた。
一年の活動の流れを聞いて、委員会内の役割を決めて、それから司書の先生に頼まれて、図書室の整理整頓をすることになった。
「紫藤先輩、すみません……、今日部活がどうしても抜けられなくて……!」
「お、俺も、家の用事が……」
「いいよ、いいよ。用事がある人はそっち優先して。俺は時間あるし、先生の用事は任せといて」
「ありがとうございます〜!」
「けど次は頼んだぞ〜?」
さっさと帰って行く人たちを見送って、さてと、と周りを見渡した。
残ったのは数名。まあ、面倒ごとではあるから、一人じゃないだけマシだろう。
「じゃあ、みんなでやっていこうか。えっと、分担は」
「あたし、本の整理してくるから。カウンターの整理と備品整理、よろしく」
初めて、こいつと話した気がする。
いや委員会で一緒になった時は会話めいたことはしたけれど、直接こいつから声をかけてきたのは初めてだった。
「えーっと、本の整理、ありがたいけど重くない? 箱詰めされてたし、男子がやった方がよくないか?」
「背丈変わらないのに? というか、段ボールごと運ぶわけないでしょ。じゃあ、そっちよろしく」
俺の返答を聞かずに、新しい本が詰まっている段ボールに向かっていってしまった。
かなり面食らった顔をしていたのだろう。同じく取り残されたメンツは苦笑していた。
「あの子、いつもあんな感じなの?」
「いや……、俺もあんまり話したことなくってさ」
「一匹狼って感じだよねえ。まあ、こうやって残ってくれてるってことはいい子なんだろうけど」
「確かに。それはそうだなあ。俺たちっていい子すぎない?」
「あはは、紫藤が言うとちょっと軽くなるなあ」
「せっかく優等生ポイント稼いでるのにね〜」
「え〜、ひどくない? ……と、冗談は置いておいて、始めてこっか。早く終わったら、先生にご褒美ねだろう」
「賛成〜」
と、一致団結して黙々とやったおかげで、作業はすぐに終わった。一番大変だろう作業を、あいつが持っていってくれたからでもあるだろう。司書の先生はお礼を言って、こっそり駄菓子をくれた。
駄菓子を隠し持って、他の子たちが帰っていくなか、最後の段ボールを開けていたあいつは、俺たちに声をかけることなく一人で作業を続けていた。
「手伝うよ」
「いらない」
声を掛ければ、取り付く島がないほどの拒否を受けて、また面を食らった。
「あはは。でもさ、一人でやるより二人でやった方が早いと思うけど」
「……紫藤、そんなに本読まないんでしょ。しまう場所分かるの?」
苗字、知ってたんだ。
絶対覚えられていないと思っていた。表情には出していないつもりだったが、見透かされていたらしい。クラスメイトの苗字くらい覚えてる、と冷たい声で言われた。
「からかうつもりなら帰って。紫藤は自分の作業終わったんでしょう? ならあたしの作業を手伝う必要ないと思う。というか邪魔」
そう言って、俺から興味を失ったようだ。
また一冊手に取って、片付けを再開してしまった。
再び取り残された俺は、かなり戸惑っていた。
それなりに人付き合いは上手い方だと思っていたが、女子からこんな対応されたのは初めてに近い。……なんというか、幼馴染——つまり清澄の女子版を見ているような感覚だ。あいつもあいつで、率直過ぎてよく相手を泣かせるのだが、少し離れたところで冷静に聞いていると、意外と的外れなことは言っていないのだ。言い方が、ものすごーく悪いだけで。まあ、あいつよりキツい気がするが、多分それは関係値もあるだろう。
ともかく、清澄に鍛えられた感覚によれば、黙々と作業を続けるこいつは、俺のことを気遣ってくれているのだと、思う。担当分終わらせたならとっとと帰れと。
「やっぱり、手伝うよ」
俺が本を手に取ってそう告げれば、こいつは明らかに「なんだこの男子」という表情を浮かべた。
それからやっぱり冷たい声で言うのだ。
「いらないって言ってるんだけど……。他の人帰ったんでしょ」
「他の人は他の人だろ? 二人でやった方が早いって。これ、どこにしまえばいいかな」
笑ってじっと見つめれば、ため息を吐かれた。
そして少しの間俺のことを睨みつけていたが、俺が笑顔を崩さないままでいたら、最終的に本の背表紙を指さす。
「…………ラベル見て。本棚にも表示書いてあるから、あとはそれ見て番号順に並べるだけ」
「あ、本当だ。これ先生ラベル貼るの大変だっただろうなあ……。これこそ俺たちに手伝わせればよかったのに」
「本の扱いがなってない人もいるのに? 正気じゃない。背表紙がぐちゃぐちゃになって終わりに決まってる」
「否定はしないけど。でも、お前がやったら結構いい感じにやりそうだな?」
「は? あんたがあたしの何知ってるって言うの」
褒めたのに、本気で意味が分からない、という顔をしている。
お世辞なら他を当たって、と迷惑そうに手を振られるから、違うってと俺は首を振る。
「だってさっきから無駄なく片付けてるな〜って思って見てたから? 俺よりは図書室来てるんだな、って思ったし、本の触り方見ても、本が好きなんだなって分かるし、出来そうだって思うのは当然じゃない?」
今度は眉間に皺を寄せられてしまった。
見過ぎだったかもしれないな、と思ったが、他の人たちだって思っていたことだろうし、とこいつの動きを見守っていたら、ふい、と顔を背けられた。
「……紫藤って、疲れそうな生き方してるね」
至極興味なさそうな顔で言われたことに、咄嗟にいい感じの返答を作ることが出来なかった。
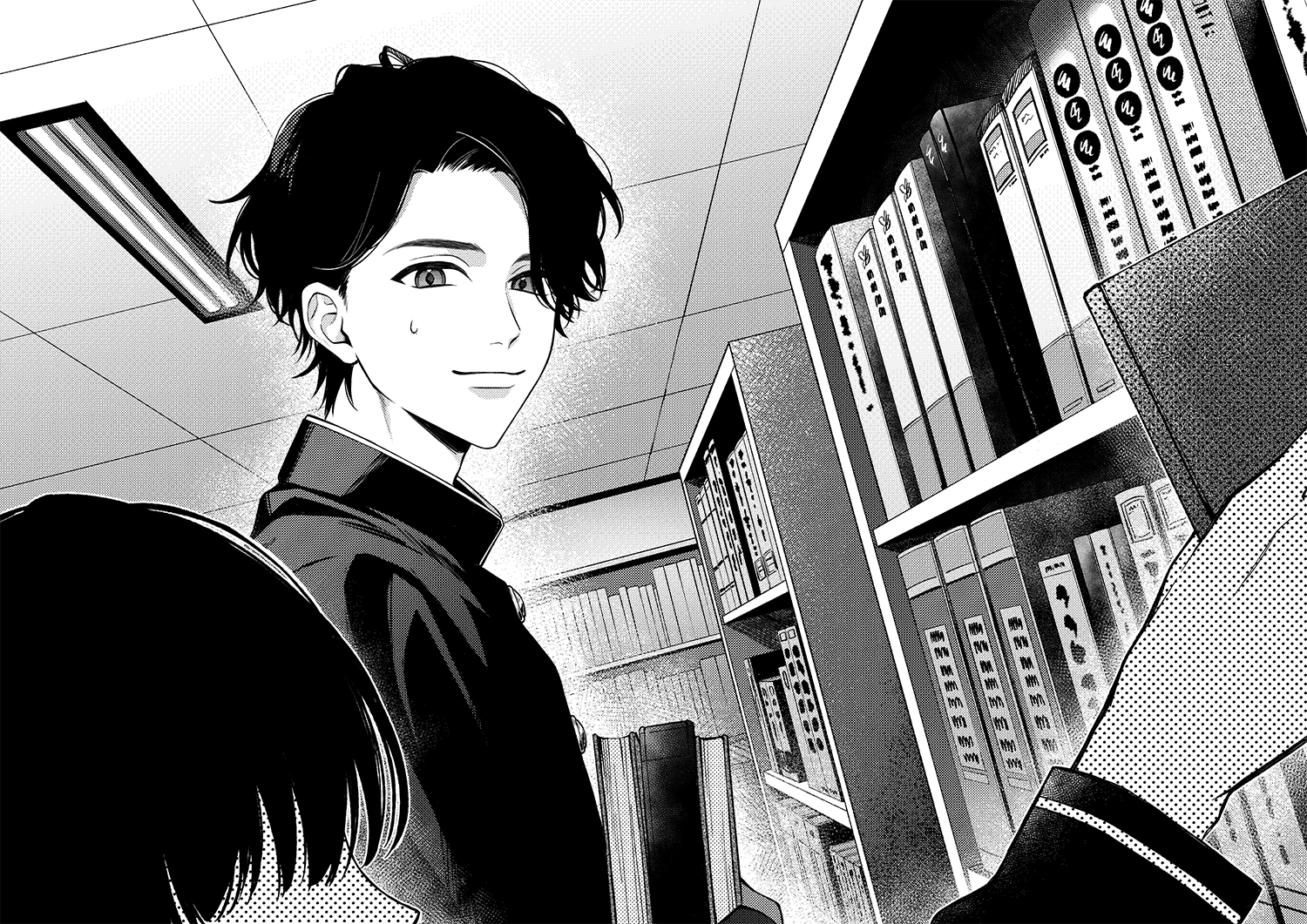
「え、いきなり、なに?」
「人のことばっかり見て、気遣って、それなりに立ち回るの、疲れそうって思っただけ」
「ええ〜? いやあ、そんなこと……」
「周り煽って、断れない雰囲気作られた上で、面倒ごと押し付けてきたら、あたしは怒る。……あんたはへらへらしてたけど、あたしはああ言うの嫌い」
吐き捨てるように言ったこいつは、次の瞬間には、もう俺のことは見ていなかった。本当に興味を失ったのだろう。本を数冊持って、さっさと作業に戻っていった。
「うわー…………」
きっかり五秒間フリーズしていた俺は、手にある文庫本の背表紙を意味なく見つめていた。
あいつが言っていたのは、図書委員決めの時のことだろうか。あんなの流されて、みんなの総意に従ったり、それが嫌なら意図的にずらす方に回った方が楽なのに、あいつはそれを真っ向から拒否するんだと思った。間違いなくその立ち回り方は波風を立てるし、孤立する。清澄がそうだから、俺は確信をもってそう言えた。教室でこいつが少し浮いているように見えるのは、もしかしたらそういった二年間の蓄積なのかもしれない。
傷つきたくないのであれば、選ばない方がいい道だ。というか、委員決めの時のクラスのああ言う雰囲気が嫌いだったとしても、さっきの言い方はキツすぎるし、今日の俺たちへの言い方はもう少し柔らかいものを選べたはずだし、そもそも冷たい目で見なくたっていいじゃないか。そう思う。
でも、俺は——俺ができないことだからこそ、嫌いになれなかった。
きっと、あいつは自分の感情に素直で、真面目で、でも意地っ張りで、不器用なんだろう。
「あ、紫藤くんまだ残ってたのー? あら、新刊整理の方もやってくれていたのね」
「ああ、先生。俺は最後の手伝いだけです。あの子がほぼやってくれてたので」
「あらあら、じゃあご褒美は上乗せしないとね」
「そうですよ。三倍にしてあげてください」
ちょっと強めに言って、俺はあいつよりも数倍は遅いスピードで本を片付ける。
お前だって、かなり疲れそうな生き方しているように、俺には思えるよ。
……でも、だからか、俺は仲良くなりたいな、なんて思ったのだ。
