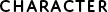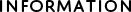Special
Happy Birthday 八神 十識
七月十七日。ふと俺がスマホを確認すると、未読メッセージが一件入っていた。
差出人は杏樹から。
「明日いつものするよ」
簡潔すぎるそのメッセージに、俺の口から思わずため息が漏れる。まったく、最初から俺の明日の予定がない前提で話を進めやがって。まあ、実際何も入れていないんだが。
いつからか、俺と杏樹はお互いの誕生日には必ず祝いあうようになっていた。それは長年の習慣みたいなもので、一時はあいつと三人で祝うこともあったけど今はまた二人だけに戻っている。
俺が了承の返事を送ると、少しの間があって杏樹から明日の待ち合わせ時間と場所が送られてくる。それを見て、俺はまた今年も自分の誕生日が来たのだと今更ながら実感した。
翌日、俺は指定された場所に時間通りに着いたが、杏樹はまだ来ていなかった。
夏の鋭い陽射しを避けて俺が日陰でまっていると、十分ほど遅れて杏樹がやってきた。
「お前さあ、寝坊しただろ」
俺が開口一番にそういえば、杏樹の顔がむっと膨れる。
「そんなことない、ちょっと遅れただけ」
「髪の毛、寝癖ついてるぞ」
「え、どこ?」
「ここ」
慌てて髪の毛をあちこち触り始める杏樹を笑いつつ、俺は寝癖でそりかえった部分を手櫛で整えてやった。不本意そうな杏樹の顔が面白い。
「んじゃ、行こうか」
杏樹の寝癖もだいぶ落ち着いたあと、俺がそう言えば杏樹は無言で頷く。杏樹をエスコートするような形で歩き出しつつ、これじゃどっちが誕生日なのか分からないなと俺は小さく笑った。
誕生日ケーキを食べるという名目で、杏樹が行きたがっていたスイーツの店をいくつも巡って腹も充分膨れた頃、外の日はすっかり傾き始めていた。
俺たちは解散することなく街を離れ、そのまま川辺の方まで歩く。土手に降りて手近にあったベンチに座ると、水辺の涼しい空気が俺たちを出迎えてくれた。
「で? 最近どうなんだ」
隣に座った杏樹に、俺はいつものように話しかける。こうやって、お互いの近況や何気ないことを話題が尽きるまで喋るのも誕生日の"恒例"と言うやつだった。
「んー……特に」
「いや、今回はいろいろあっただろ、大学のこととか」
ぼんやりとした返答をする杏樹に、俺は思わず言及してしまう。
そして、そのまま俺たちは他愛ない話に花を咲かせた。花を咲かせる、と言っても元々杏樹は口数が多い方ではないし、普段は会話の盛り上げ役をする俺も杏樹には気を遣わないため、話はそれほど盛り上がらない。話題が突然終わって、そのまましばらく無言になることも多い。だけど、無言になっても互いに気を遣わずぼーっと出来るこの関係は嫌いじゃない。
「あ、カップルがいる!」
会話が途切れ、何度目かの沈黙、突然の声に視線を上げれば、河川敷で遊んでいた子どもたちが近くまで来ていた。
「カップルがこんなとこで何やってんだよ!」
「やーらしい!」
そう囃し立てる子どもたちに、俺は思わず苦笑いを浮べる。何気なく隣の様子を伺えば、杏樹は相変わらず涼しい顔のままだった。
「こーら、大人をからかうんじゃない。それに、誕生日を祝ってもらってただけだから何もやらしいことなんてしてないからな?」
「たんじょうびぃ?」
「そう。お兄さん、今日誕生日なんだよ。だから、お前たちも祝ってくれていいんだぞー?」
俺の大人の対応に、子どもたちは困惑したように顔を見合わせる。
「ふーーん、誕生日おめでとーな! おっさん!」
にやにやと笑いながら子どもたちはそう言い放ち、蜘蛛の子を散らしたように走り去っていく。
「おい! おっさんじゃくてお兄さんだろ、こら!」
俺が大声でそう叱るも、子どもたちの笑い声が遠くに聞こえるだけだった。杏樹はというと「おっさん……」と何度も呟きながら笑い声を漏らしていた。
「はあ……」
子どもたちの姿も見えなくなり、空が本格的に夜の気配を滲ませ始めた頃、俺は何気なく大きなため息を漏らす。
「どうしたの?」
杏樹が珍しく突っ込んできたことに驚きつつも、俺は誤魔化すようにため息の先の言葉を続ける。
「いやさあ。いつまでこうして杏樹に誕生日を祝ってもらえるんだろうなーって思って」
「そんなの、十識が望むまでだよ」
「さすがは杏樹さん。イケメンすぎて惚れそう」
杏樹の男前すぎる答えに、俺は照れ隠しがてら茶化しつつ答える。そんな俺の様子からなにか読みとったのか、杏樹はくしゃりと表情を崩しながら笑った。
ゆっくりと日が沈んでいき当たりが暗くなっても、俺たちはまだベンチに座ったまま、何気ない話を続ける。
世の中に、変わらないものは無い。時間がゆっくり進んでいくように、俺たちの変わらないと思っている関係も俺たちが気づかないうちにゆっくりと変化していくのかもしれない。
それでも、このサプライズもなければ、特別感もない、ただいつもよりも少しいいご馳走を食べて、今更プレゼントを送り合うこともなく、こうやって川辺で涼みながらだらだらと話しているこの時間が、俺はとても気に入っている。特別な日なのに、特別なことをすることなく杏樹と過ごすこの時間が、俺にとっては何よりのプレゼントだから。
そんなことを伝えようと、杏樹の方を見るとふいに目が合う。杏樹も何か言いたいことがあったようだ。
「誕生日おめでとう、おっさん」
俺が口を開く前に、杏樹が淡々とそう告げる。
「おう。サンキューな……って誰がおっさんだ、誰が」
意趣返しのように俺が頭をわしわしと強く撫でれば、杏樹の笑い声が静かな土手に響いた。
もし今後、俺たちの関係が変わることがあったとしても、この特別じゃない時間を大切にし続けたい。俺は、心からそう思った。