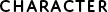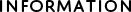Special
プロローグストーリー・Side 八神 十識
一度部屋にこもるとなかなか出てこない杏樹を、餌付けと称してカフェに呼び出すのは昔から俺の役目だった。
杏樹は集中すると時間どころか寝食すら忘れて没頭してしまうようで、タイミングを見計らってこうして呼び出してやらないと、倒れていないか不安になる。連絡が取れなくなった杏樹を心配して部屋に飛び込んでみたら、一心不乱に絵に向かっていた……なんてことも一度や二度ではない。
課題の締め切り的にそろそろ呼び出してやる時期かと思っていたけれど、俺のスマホに表示されていたのは、俺から杏樹へのメッセージではなく杏樹から俺へのメッセージ。
『いつものカフェに来れる?』
珍しい誘いの言葉に思わず空を見てみるけれど、雨が降りそうな気配はない。
(あっちから連絡なんて、何か心境の変化が……って杏樹に限ってそれはないか)
杏樹のことは、俺が一番知っている。それこそ杏樹よりも知っている事もたくさんあるだろう。
(どんな用事かは……実際に本人に聞いてみれば分かるか)
俺は行きつけのカフェの扉を押した。
扉を開けるとほぼ同じタイミングで到着していたらしい杏樹と目があった。
「十識おはよう」
「おはよう。お前も今来たところ?」
「うん。あ、いつもの席で良いって」
「いつもの席、で通じるのも面白いな」
「それだけ来てるから」
カフェの店員に案内されていつもの窓際の席に座り、メニューを開いて杏樹に渡してみるけれど……。結局頼むものはいつもと同じになるだろう。
しばらくの間ぼんやりとメニューを眺めている杏樹に、「いつもと同じのでいい?」と問いかけてみる。
「うん」
「お腹は?」
「お腹……」
俺の言葉に「そういえば」なんて顔をするから、食べていないことが分かる。ここに来る直前まで、課題をやっていたのだろう。
「食べるの忘れてた」
「だろうな。それならサンドイッチも追加しよう。ハムとチーズのと、こっちのタマゴサンド、どっちがいい?」
「タマゴサンド」
「分かった。相変わらずここのタマゴサンド好きだよな」
「うん、タマゴがふわふわしてておいしいから」
「そっか」
注文するものが決まった俺は、早速店員を呼んでアイスコーヒー2つとタマゴサンドを注文する。その様子を見ていた杏樹はいつも通りに見えたけれど……どこか違和感があった。
杏樹と共有してきた時間が長い俺だからこそ分かる、少しだけそわそわしているような雰囲気。
そんな杏樹の様子を横目で見ながら飲み物が運ばれてくるのを待っていると、そう時間をかけずにアイスコーヒーがやってきた。細いストローを使ってコーヒーで喉をうるおした杏樹は、ようやく俺を呼び出した本題を話し始める。
「なんか新しい家族が増えるみたい」
「……家族? 犬猫を飼うとかって話じゃなくて……」
「相手も人」
「それもそうだよな」
じゃなきゃ、ここまで緊張感のあるような話にはならないだろう。
「再婚で……新しい家の鍵もある」
「えっと?」
「黒住絃静さんって人で……」
話上手ではないからか、それともまだ杏樹自体がこの出来事をきちんと噛み砕けていないからか。杏樹の口から出てくる家族やら、再婚やら、鍵やら、ぽつぽつと出てくる言葉を受け止め、整理しながら理解していく。
杏樹の話を理解するのにも時間がかかったけれど、理解してからも疑問が湧き上がった。
「つまりまとめると、おばさんの再婚で杏樹に家族が増えて、その家族が黒住絃静さんだった、と」
「うん」
「鍵を渡されたってことは、同居するってことなんだよな?」
「そうみたい」
「……なるほど」
杏樹とは家族ぐるみの付き合いをしていたので、当然杏樹の母親であるおばさんにもいつもよくしてもらっていた。俺は杏樹の父親が亡くなった時もそばにいた。だからこそ、再婚でおばさんが幸せになるのは純粋に嬉しい。
(だけど……)
家族になって同居する人物の名前を聞いて、驚きと不安がないまぜになった。驚きよりも、不安の気持ちの方がはるかに大きいだろう。
(よりにもよって黒住絃静、か)
黒住絃静は俺たちが通う大学で同じ専攻をしている人物で、構内でもかなり有名だ。それなりに人数が多い大学なのにもかかわらず有名、と言うことは、その人に何かあるということに他ならない。
俺自身は彼と特別親しいわけではないから詳しくは知らないけれど、才能を持っているのに気分のむらが激しいとか、作風にも一貫性がないとか……。そんなことを言われているのを聞いたことがある。おまけに、女がらみのよくない噂もある。
(杏樹はそのことは気にしてなさそうだけど)
杏樹は元々こういった話にはうといし、気にしないだろう。そもそもこの噂を知っているかは微妙だけれど。
(なんて、俺が気にしてても仕方ないか)
そう思うことにするけれど、心に残るのは心配事ばかりだ。一緒に暮らせるのか、変なことにはならないのか、大丈夫なのか。心配も不安も言いたい事もたくさんある。
「……なあ、杏樹」
「ん?」
俺の言葉に、ストローを加えていた杏樹が首を傾げる。杏樹は言いたいことを言ってしまったからか、どこかすっきりしているようにも見えた。
(黒住絃静さんって人、あんまり良い噂を聞かないから気をつけて欲しい)
なんて口に出そうかと悩んで、結局やめた。代わりに口から出たのは、杏樹を気遣う言葉だった。
「今度新しい家族を俺にも紹介してくれよな」
「うん。十識には紹介したいと思ってた」
杏樹は少し戸惑った表情をしてから、こくりとうなずいた。
不安なのは、心配なのは俺だけじゃない。実際に彼と同居をするのは杏樹なのだから、顔に出なくても俺以上に不安だし心配に違いない。
それに気をつけろと言って、杏樹の新しい家族をはじめから批判するようなこともしたくなかった。
(だとしたら、俺にできることはひとつだよな)
俺が黒住絃静という人物を信用したいなら、まず俺から信用してみよう。疑いの気持ちがどこかに少しでもあれば、信用できるものもできなくなってしまうだろうから。そして信用できると分かったうえで、見守っていよう。
(それがきっと、杏樹のためになる)
忘れもしないあの日から、俺と杏樹はずっと一緒にいた。そうやって互いの傷をかばい合い、気持ちに寄り添うことで、消えることのない思い出を大切にしてきた。
今までもそうしてきたから、これからもそうしていく。
杏樹が誰と同居することになっても、家族が増えても、それは俺たちの間で変わることはないだろうから。
お待たせしました、と言う声が聞こえてふっと我に返ると、テーブルの上に頼んでいた卵サンドイッチが置かれた。杏樹がタマゴがふわふわでおいしいと言ったからか、タマゴの柔らかな黄色がやけに目についた。
「そういえば最後に食べたのいつなんだ?」
「ん? このタマゴサンドじゃなくて……」
「その前のって話」
「……昨日の夜にメロンパン? 違った、昼だったかも」
その言葉だけで、杏樹がいかに集中して課題に取り組んでいたのかが分かる。
「まったくお前は~~~。まあ、いっか。冷めないうちに、早く食べな」
「うん」
いただきます、とつぶやいてから杏樹はタマゴサンドにかぶりつく。
「おいしい」
もぐもぐと口を動かしながら、杏樹は嬉しそうに笑った。俺はその笑顔に目が離せなくなる。それは太陽のような明るくて元気な笑顔とは違い、どこか静かで柔らかく優しい雨の雫のような笑顔。そんな笑顔に、ずっと惹かれている。
「サンドイッチは逃げないから、ちゃんと噛んでゆっくり食べな」
俺はこの笑顔と、それから、杏樹にすら信じてもらえない杏樹の才能を失われないようにするためなら、なんだってできる。そんなふうに改めて心に誓った――。