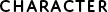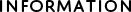Special
プロローグストーリー・Side 黒住 絃静
「何で、お前らと帰らないといけないんだ……」
「えー、いいじゃん。どうせ同じ方向に行くんだし」
「そうそう。それなら、一緒に帰っても帰らなくても大差はないよな」
「いや……大違いだろ」
大学の帰り、一人で帰ろうとした蒼士を見つけて、「一緒に帰ろう」と縁と一緒になって捕まえる。蒼士は心底嫌そうな顔でため息をついたあと、諦めたように歩調を緩めてくれた。
「そういや、次の課題のテーマってもう決めた? 俺まだ決めてないんだよな」
「とっくに決めている」
「まじかよ、さっすが蒼士ー! 絃静は?」
「もう決めたよ。てか、すでに描き始めてる。今日、何枚かラフ描いたから、その中から決めるつもり」
最寄り駅まで向かう途中、何気なく振られた話題に何事もなく答えれば、縁から心底驚いたような声が返ってくる。
「はぁーー!? 嘘だろー!? じゃあ、決まってないの俺だけ?」
「お前が遅すぎるんだ」
「提出は来週だからな、縁も急いだ方が良いぞ。頑張れ」
「くっそー……二人とも俺のことを裏切りやがってーー!」
縁の断末魔に苦笑していると、ふとズボンのポケットの中でスマホが振動し始める。手に取ったときには止まってしまったそれを何気なく確認すると、表示された名前に思わず手が止まった。
「何? オンナ?」
茶化したように小指だけをあげて聞いてくる縁に、「違う、何でもない」と軽く返す。蒼士は全く関心がないのか、こちらを見ることなく黙々と駅に向かっている。
さすがにこの二人の前では掛け直せないと思い、通話ボタンを押すことなくスマホをポケットに戻した。
「掛け直さなくていいのか?」
「あとで掛け直すから、気にしなくていいよ。ところで、さっきの話の続きだけど。テーマの件、一緒に考えてやろうか?」
「うわー! ありがてー!! 神様仏様、絃静様!!」
「丁度、蒼士もいるしな」
「……俺は手伝うと一言も言ってないんだが」
「まぁ、人助けだと思って」
案の定、渋る蒼士をそう宥めつつ、三人で縁の課題テーマの話をしながら駅に向かう。……その足取りが、ほんの少し重いのはきっと二人には気づかれていなかったと思う。
駅で二人と別れ、自宅の最寄り駅について自分一人になったところでスマホを取り出した。ざわりとした胸騒ぎを感じつつも、相手が電話に出るのを待つ。コール音が五回鳴ったところで、ようやく淡々とした男の声が電話に出た。
そして、挨拶もそこそこに電話先の彼は、電話をしてきた要件だけを話し始めた。まるで、仕事先の人間とでも話すかのように。
「……うん、わかった。じゃあね、父さん」
適当な相槌を続けた後、そう言って父との電話を切る。だけど、心の中では父に告げられた話の数々を飲み込めないままでいた。課題のテーマを早々に決められたこともあって、今日は一日そのラフを描き続けて、黙々とテーマに向かい合うことができて、いつもよりも良い気分だったのに、今は複雑な気分だった。
改札から出て、外の空気を思いっきり吸って吐くと、吐息は夜の闇の中へ溶けていった。きっと、口では「わかった」と言えても、心はまったく理解できていないのだと思う。
家族が増えること、母親ができること、妹ができること、その子と同居するこことになること、そして同じ大学に通ってること……父が伝えてきた話はまるで情報の洪水のようだった。だけど、それを事務的に連絡していた父の声は、いつもよりもほんの少し温度がある気がした。
恋人でもない女の子と、家族として一つ屋根の下で暮らすことになる。それを、相手は……まだ顔も名前も知らない妹はどう考えているのか、そしてそれをこちらはどう受け止めれば良いのか。
家路への道を歩きながら、もう一度大きく息を吐きだした。本当に吐き出したいのは、息ではなく、忘れられない過去だった。それを思い出せば、ずきりとした痛みが右手に疼く。大丈夫だ、今はあの頃と違って自分でどうにかできないような子どもじゃない。何があっても、最低限自分の身を守ることはできる。そう、自分自身に言い聞かせながら頭の中に蘇る過去を必死に振り払う。
家への道はすっかり暗くなっていて、夜空には星が輝き始めていた。その光に、幼い頃ベランダから見た星を思い出しそうになって、思わず下を向いてしまう。街の光で隠されて見えないだけで、星はいつだって頭上にある。もちろん、絃静の頭の上にも。そう笑いながら教えてくれたのは母親と父親どっちだっただろう。今となっては、どうでもいいことなのだが。
血が繋がっていても幸せになれない家族があれば、血が繋がらなくても幸せになれる家族だってある。そもそも結婚だって、血が繋がっていない者同士が家族になることだ。はたして、これから始まる血の繋がらない家族は、幸せな家族になれるだろうか。
「……そうなれるといいんだけど」
三度目の吐息と一緒に漏れた言葉は、完全に無意識のものだった。幸せな家族なんて、もうとうに諦めていたつもりだったのに。まだ諦めきれない自分に気がついてしまって、悲しいような、苦しいような、胸が締め付けられる気持ちになる。
そんな感情をごまかそうとして、ふいに夜空を見上げる。そこには、真っ暗な闇の中で光り輝く大きな月が浮かんでいた。