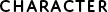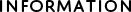Special
Happy Birthday 窪田 縁
俺の馴染みのバーは、店主が気まぐれに生演奏をすることがある。なんでも昔ジャズを齧ったことがあるとかないとかで、知り合いを呼んで演奏をすることもあれば、店主が演奏することもあり、今日はそのどちらでもない日だったらしい。
品のいい音の代わりに聞こえるのは、店内BGMとしてCDから流れるジャズと、わいわいとした喧騒。今日は平日ではあったが店にはそれなりの人数の客がいて、誰もが楽しそうに飲んでいるようだった。
そんな喧騒から少し離れたところで注文したカクテルを飲みながら待つこと、十数分。ようやく俺を呼び出した張本人が現れる。そしてそいつは当たり前のように俺の隣に座った。
挨拶をするよりも早く、メニューを見ながら何を注文するのか迷っているのを見ていると……無遠慮な視線が俺たちに突き刺さるのを感じた。
(ま、こんなところで男二人で並んで座ってればな)
こんな男女の出会いの場のようなバーで、俺たちが並んで座っているのがよほど珍しいらしい。女の子たちがどこか値踏みするような視線とともに、俺たちを遠巻きに見ているのがわかった。
(中身はともかく、外面はいい方だし)
そんなとびきり熱い視線を無視しているのか、それとも気づいていないのか……待ち人である絃静は、偶然にも俺と同じカクテルを注文したらしかった。絃静は、自分に向けられる視線には存外無頓着だ。
注文をしてから、俺の飲んでいるカクテルに気づいたらしい。
「あ、それもしかして同じの?」
「そう」
「なんだ、同じのって分かってたら別のやつ注文しようかと思ったのに」
それはどういう意味だろうか。俺の無言の圧を感じ取ったのか、そっとフォローらしきものを入れた。
「同じやつのなら一口もらってもいいかなって」
「自分で飲む分は自分で注文しろっての」
数時間前に、急遽シフトに入っていなかった絃静に呼び出された。俺はバイトが入っていたから集合時間をずらしてもらったが、到着は絃静のほうが遅かったようだ。今更少しくらい遅れることは気にすることもない間柄だ。
「縁の方が早かったんだ、もっとかかると思ってたけど」
「今日は店長いたからな、その辺の面倒な作業は全部やってくれるってさ」
「なるほどね。今日はどんな感じだった?」
「どんな感じって言われても……まぁいつも通りって感じだな。店長はテンション高いし、お客さんは若い子が多いし」
「そりゃいつも通りだ」
俺と絃静は同じ店でバイトをしており、この辺の事情はよくわかっている。
手元のカクテルを煽ると、待ち人をしていた時よりも不思議と美味いような気がした。程よい労働で疲れているからだろう、と思うことにする。
「お、きたきた〜乾杯!」
「乾杯、乾杯」
すぐに絃静の注文したカクテルが運ばれてきて、俺たちは乾杯した。喉が渇いていたのか、絃静は一気にグラスの半分ほどを飲んでいた。空きっ腹だとしたら、これは酔いが回るのが早そうだと思うが……そうなったらそうなったで酔った絃静が見られて面白いのでいいか、と思う。まあ、絃静もそこまでは弱くないけれど。
「で、用事って何?」
「じゃじゃーん」
「……その効果音ダッサ」
「いいだろ、分かりやすくて。何かが出てくるって感じがしてさ」
「そうか? まあ、ぱんぱかぱーんよりはいいけど」
俺に問われた絃静は、にやにやしながらカバンの中から何かを取り出す。それはラッピングされた、片手に乗るほどの小さな箱だった。まるで、その小さな箱の中には指輪でも入っているようなサイズだ。
「なにこれ、誰かにプロポーズでもすんの?」
違うし、なんて言葉が返ってくることが分かりつつもそう問いかけてみた。……冷静に考えると、シチュエーション的に相手は俺、ということになる。
「……なんだよその顔」
「プロポーズすんの、って自分で聞いててちょっと鳥肌たった」
「はいはい。お前に誕生日プレゼント」
「……ああ、そっか。今日か」
言われてから、今日が誕生日だったことを思い出す。言われてみればそうだった。
貰ったものだからもうどう扱おうと自由だろう、と早速ラッピングを剥がしてプレゼントを確かめることにする。
「……女みたいなプレゼントくれるじゃん」
小さな箱の中から出てきたのは指輪ではなくジッポで、つい茶化すような言葉が口から漏れた。
「たまたま見かけて、これしか考えられなくなったんだよ」
「……そ」
絃静は静かに笑っていた。
そこそこ長い付き合いの俺たちは、毎度気まぐれに互いの誕生日を祝ってきた。気まぐれだから、プレゼントがある時もあれば、ない時もある。今回はある時だったようで、ありがたく頂戴することにする。
「ありがとな」
きっとこの関係性は、これからも続いていくんだろうなと思っている。
俺は貰ったばかりのジッポを眺めながらポケットからタバコを取り出した。そして手持ちのライターで火をつけて吸う。口の中に広がるのはいつも通りのもののはずなのに、妙に美味いと感じてしまう俺がいる。
「使わないの?」
「せっかくだしもうちょっと堪能してからにする」
「堪能もなにもないと思うけど」
「あるんだよ」
「そう」
絃静はそんな適当な言葉に納得してくれたようで、カクテルに口をつけた。
何かを自分の所有物にする感覚は、昔から好きだ。だけど手に入れてすぐのときは、自分の手に馴染むまでは、どう扱えばいいのか戸惑う。
手に入れたいのに、いざ手に入れたら入れたで戸惑いがあって。
(……難儀なもんだな)
そんな気持ちのことを、目の前の男は到底理解できないんだろう。今までも、きっとこれからも。
そんなことに何か思うことがある部分もあれば、そのままでいてくれと思う部分もある。この複雑な気持ちは言葉にならない、不思議な色をしている。
「ま、お返し期待してるから」
「はいはい。今から半年後だけど、考えとくよ」
「半年も先だと忘れそうだけど」
「そしたらその時はプレゼントがない時ってことだな」
楽しそうに笑う絃静を見ながら、俺は吐き出せない気持ちの代わりに煙を吸い込んで吐き出した。
今日は、誕生日。だったら少しくらい羽目を外したって許されるだろう。そろそろ空になるグラスを見て、追加を注文する。
「同じのください」
「あ、こっちも同じのもう一つ」
「……仲良しかよ」
「悪いよりはいいだろ?」
「まあな」
少し離れたところに座り俺たちに熱い視線を送ってくる女の子たちに視線を送れば、何かを期待する表情の彼女たちはグラスを持ってこちらにやってくる気配がする。
「ほんと、縁はこういうの好きだよな」
「まあな」
甘い気持ちも苦い気持ちも全部酒で流し込んで、俺は一年に一度の夜に溶けてゆくことにした。