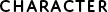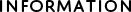Special
プロローグストーリー・Side 妃 杏樹
幼い頃を思い出すと、決まって最初に思い浮かぶのは絵を描く父の背中だった。
私が部屋の入り口で父の後ろ姿を見ていると、父は決まって振り返って「おいで」と優しい声で手招きしてくれた。
それぞれ違う色が入れられている、たくさんの絵皿。その中のひとつの色を父が絵筆で掬って下絵の上に載せれば、それはまた違った色になる。それが、まるで魔法のようで幼い頃の私は夢中で父の絵を見るのが大好きだった。
顔料の匂いがこもった父の部屋と、父の手によってどんどん表情を変えていく絵、それが幼い私にとって世界の全てだった。
父が亡くなって気がつけば、数年の月日が経っていた。
この数年間、父を亡くした後も私を女手一つで育ててくれた母の苦労は相当のものだっただろうし、心から感謝している。
だけど、仕事が忙しくなるにつれて母の顔からは昔のような笑顔は消えていき、会話をしながら一緒に夕食をとるといった機会もどんどん減っていった。母と会話をすることなく一日が終わる日も少なくはなかった。
仕方がないと頭では分かっていても、寂しくないと言えば嘘になる。だけど、家族と過ごす時間の代わりに、十識や中学で仲良くなった親友と過ごしたり、一人で絵を描いて過ごしたりして、次第に気にならなくなっていった。
特に十識は私が家に一人でいることを気遣って、「一緒に夕飯でもどうだ」とよく自宅に誘ってくれた。一人だと夕飯を適当に済ませてしまいがちなことを、十識はお見通しだったようだ。十識のお母さんのご飯は美味しかったし、十識の家族はいつだって私のことを温かく迎えてくれた。
家に誰も居なくても、学校に行けば十識も親友もいる。放課後には、美術室で思う存分絵を描いていられる。
そんな毎日の中、次第に私の関心は家の方には向かなくなっていった。
ある日の朝。
今日は早く帰れるからと、珍しく母から外食に誘われた。少し驚いたが、私が「いいよ」と返答すると、母は途端にほっとした顔になる。その表情に、私はなんともいえない気持ちになった。放課後、私は美術室に寄らず真っ直ぐ家に帰った。今日は母と食事に行くと言ったら、家の事情を知っている十識は驚いていた。
そういえば、母と一緒に食事に行くのなんて何年ぶりだろう。そう思いながら、制服から私服に着替えて、母との待ち合わせの場所へと向かった。
時間ぴったりに待ち合わせ場所に向かうと、母はもう店の前で待っていた。私に気がついて、小さく手を振ってくれる。
「……待たせちゃった?」
「ううん、私も今来たところだから」
私がそう聞けば、母は首を横に振って微笑んだ。
母にドアを開けられて、私は店の中に足を踏み入れる。そこは、まだ私が幼い頃、家族の特別な日に父がよく連れて行ってくれた、個人経営のレストランだった。
「何食べる?」
窓際に用意されていた予約席に、向かい合わせて座ると母がメニュー表を手渡してくれる。久しぶりの母との会話で何を話して良い物か分からなかったのもあって、私はそれを素直に受け取ったあと、メニュー表に視線を落とした。ぱらぱらとページを捲ると、メニュー表の中の料理は、昔と何一つ変わっていなかった。
「……チーズハンバーグ」
「杏樹は昔から、それが好きね」
子どもの頃に決まって頼んでいた料理を言えば、母が小さく笑った。正直、私は母が自分の好物を思えていたことに内心驚いてしまった。
呼び止めたウエイターに二人分の料理を注文し、料理を待っている間、母は当たり障りのない話題を投げかけてくる。「学校はどう?」「友達は出来た?」「十識くんは元気?」……そういった、上面をなぞるような会話に適当な返答を返していると、ウエイターが湯気の立った料理を持ってきた。
私は目の前に置かれたチーズハンバーグを切り分けて、口の中に入れる。幼い頃からの好物は、記憶のままの味だった。昔はよく冷まさずに食べようとして、口の中を火傷していたことを思い出す。
「あのね、杏樹」
ハンバーグの味を堪能していると、母が真剣な顔で話を切り出してきた。母は昔から、こういうときのタイミングが少しずれている。
「なに?」
「……再婚しようと思うの」
その言葉を聞いた瞬間、あぁやっぱりと私はどこか腑に落ちた気持ちになった。母が何もないのに、私を外食に誘うわけがないし、いつかはこんな日が来るんじゃないかと予想していたのもあったからだ。
十識には、その日が来たら応援してやれよと言われていた。だけど、何も父が好きだったこのレストランで言わなくてもいいんじゃないのか。母の再婚よりも、私はそっちの方にショックを受けていた。
「相手にも子どもがいるの。丁度、あなたくらいの。名前は――」
母の話に気のない相づちを打ちながら、父がまだ生きていた頃の思い出が蘇ってくる。
注文した料理を見ながら、この料理はどの色で描いたら綺麗に見えるだろうか、どう描いたら美味しそうに見えるだろうかと父と話すのが私は大好きだった。
「料理も、絵も、そして杏樹にも無限の可能性がある。だから、面白いんだ」
私の頭を撫でながら笑っていた父と、そんな私達を幸せそうに見守っていた母。その母の顔は、だんだん目の前の母へと変わっていく。
「……どうかな、杏樹」
目の前の母は、罰が悪そうな、機嫌を伺うような作り笑いで、私の返答を待っていた。いつの間に、母はあんなに風に笑わなくなってしまったんだろう。あの時、家族三人で楽しそうに笑っていた母は一体どこに行ってしまったのだろう。
「……うん、いいんじゃないかな」
「よかった……杏樹ならそう言ってくれると思っていたわ」
私が適当に返事をすれば母は心底安堵したように、小さく息を吐いた。もう、あの頃の私と母ではなくなってしまったと実感しつつも、そんな母を見ていられなくて私は黙々と料理を口に運んだ。
その後、私は母の説明を録に聞かずに返答してしまったことを後悔することになる。
まさか、男の子と二人、同じ部屋で住むことになるだなんて、思ってもいなかったのだ。
その事を十識に告げたら、盛大に呆れられて心配されてしまったけど、ずっと一人っ子だった私は自分に兄弟ができることに、ほんの少しだけわくわくしていたのだった。